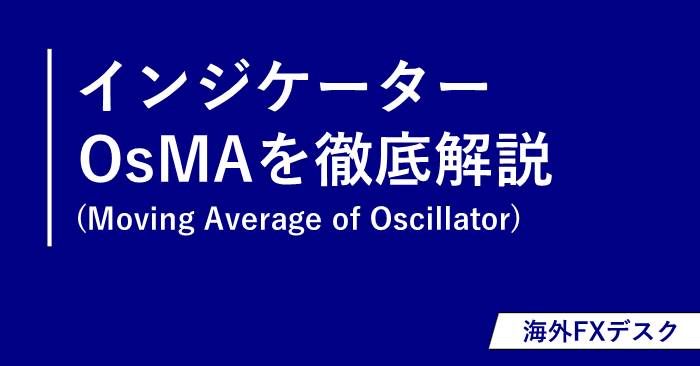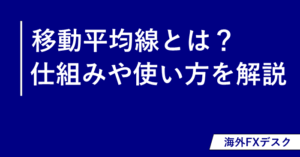オシレーター系のインジケーター「Moving Average of Oscillator(OsMA)」を詳しく解説。
Moving Average of Oscillator(OsMA)の仕組みや使い方、利用時に注意したいポイント、普通の移動平均線(MA)との違いについて紹介します。
\今ならここから登録で13000円ボーナスあり/
\元金不要で始められます/
【入力4分】XM公式
口座開設はこちら(無料)
【おすすめ選択肢】
ブランド名:FSA
口座タイプ:スタンダード
取引ツール:MT5
移動平均線(MA)とMoving Average of Oscillator(OsMA)の違い
移動平均線(MA)は価格そのものの平均です。
チャート上には一定期間の終値などを平滑化した数値を結んだ曲線で描写されていて、その時点の価格がMAより上か下か、傾きが上向きか下向きかをトレンド判断の目安にします。
(あくまで目安で確定ではありません)
いわば「道のり」よりも「現在地」をなめらかに示す指標です。
一方OsMAはMACD(マックディー)というオシレーター系インジケーターとそのシグナルとの差=MACDヒストグラムのことです。
【インジケーター(Indicator)】
相場分析を補助する指標の総称。移動平均線(MA)やボリンジャーバンド、RSIなど価格・トレンド・ボラティリティ・出来高を数値やラインで可視化し、エントリーや環境認識、リスク管理の根拠に使います。
【オシレーター(Oscillator)】
インジケーターのジャンル的なもので、買われすぎ・売られすぎ・相場の強弱を0–100などの範囲で振動表示する指標を教えてくれるインジケーター全般を指します。RSI、ストキャス、MACDなどが代表的。トレンド中の逆張りには弱く、レンジ相場や押し目・戻りのタイミング判定の補助として有効です。
価格の平均ではなく「勢いの加速・減速」を数値化します。
MAのシグナルは価格×線の交差や傾き、OsMAはゼロラインと棒の伸縮、ダイバージェンスで読むのが基本。
MAは遅行でも安定したトレンド把握、OsMAはタイミングや勢いの質感を補う役割で、両者は競合ではなく分業が前提です。
Moving Average of Oscillator(OsMA)とは?

OsMAはMACDラインとシグナルラインの差(MACDヒストグラム)を表示するオシレーター系インジケーターです。
ゼロより上なら上昇圧力が優勢、下なら下降圧力が優勢。棒が伸びると加速、縮むと減速を示し、トレンドの勢いを視覚的に把握できます。
オシレーター:相場の勢いを上下帯で示す指標
MACD:短長2本のEMA差で勢いを測る指標
シグナルライン:MACDの移動平均
ヒストグラム:棒グラフ表示のこと
Moving Average of Oscillator(OsMA)の計算式と仕組み
MACDライン=EMA12 − EMA26
シグナル=MACDを9で平滑化。
OsMA=MACD − シグナル(ヒストグラム)
ゼロをまたぐ方向で地合い、棒の長さの変化で加速と減速を読み取ります。
棒がピークを付けて縮み始めるのは勢いの鈍化サインです。
EMA:指数平滑移動平均(直近を重視)
ゼロライン:OsMAの基準線(0)
加速/減速:勢いが強まる/弱まる状態
平滑化:ギザギザをならす処理
Moving Average of Oscillator(OsMA)の設定とパラメータ
デフォルト設定は12・26・9。
12と26は短期と長期のEMA期間、9はシグナル用の平滑期間です。
短期側(12)を小さくすると敏感、長期側(26)を大きくするとトレンド重視になります。
9を大きくするとノイズは減るが遅行が増えます。
まずは12/26/9で感覚を掴み、ボラに応じて微調整しましょう。
期間:計算に使う本数
感度:値動きへの反応の速さ
ボラティリティ:値動きの大きさ
プリセット:初期設定
Moving Average of Oscillator(OsMA)の使い方
ゼロラインクロスは地合いの切り替え目安。
上抜け後に棒が拡大し続けるなら順張りが有利、縮み始めたら利確や様子見。
価格が高値更新なのにOsMAが更新できない通常ダイバージェンスは減速サイン、トレンド方向のヒドゥンダイバージェンスは継続示唆です。
手順は、上位足でゼロ位置と傾向→下位足で押し戻り+OsMA反転でタイミングを取るのが堅実です。
ゼロクロス:0をまたぐこと
ダイバージェンス:価格と指標の逆行
順張り/逆張り:トレンド方向/逆方向に乗る手法
上位足/下位足:長い/短い時間軸
エントリー/利確/損切りの型(例)
買いの場合
価格がSMA200の上、OsMAがゼロ上で拡大。
押し目のローソク反転+下位足でOsMAがマイナスからプラスへ反転でエントリー。
損切りは直近押し安値の下、利確は前回高値手前やOsMAの縮小開始で分割。
売りの場合
価格がSMA200の下、OsMAがゼロ下で拡大。
戻り売りポイントで反落+OsMAがプラスからマイナスへ反転でエントリー。
Moving Average of Oscillator(OsMA)を使うメリット
メリット
- 勢いの「強まり/弱まり」を直感的に掴める
- MAや価格アクションと分業しやすい
- ダイバージェンスで「危険サイン」を早めに察知
【メリット1】勢いの「強まり/弱まり」を直感的に掴める
OsMAは棒の伸縮でモメンタムの加速・減速が一目で分かります。
価格だけを見ていると「上がっているのに勢いは鈍化」といった質感を見落としがちですが、OsMAならピークアウトの兆しが可視化され、利確や様子見の決断が早められます。
ゼロ上維持のまま拡大なら強い、縮小なら失速という基礎ルールが分かりやすいのも利点です。
【メリット2】MAや価格アクションと分業しやすい
地合いの判定は移動平均線(例SMA200)に任せ、OsMAはタイミングと勢いの確認に専念させると判断がシンプルになります。
押し目買いなら、価格が戻って反発した瞬間にOsMAがマイナスからプラスへ反転しているかを見る、といったチェックが有効。
役割が明確で、シグナルの重複が少ないため再現性が高めやすいです。
【メリット3】ダイバージェンスで「危険サイン」を早めに察知
価格が高値更新してもOsMAが高値切り下げなら勢いの鈍化を示し、天井圏での飛び乗りや利確遅れを防げます。
逆に上昇トレンド中にOsMAだけが安値を切り上げるヒドゥンダイバージェンスは押し目完了の示唆になりやすい。
単純なクロス頼みより、質的な変化をとらえる練習に向いています。
デメリット
- レンジではシグナル多発で混乱しやすい
- パラメータ次第でノイズ過多または遅行
- 単独シグナル依存で期待値が不安定
【デメリット1】レンジではシグナル多発で混乱しやすい
値幅が狭いレンジでは、OsMAがゼロ近辺で小刻みに行き来し、クロスや伸縮サインが頻発します。
方向性のない環境で拾い続けると勝率が崩れやすいのが難点。
対策は、長期線(SMA200)や価格のレンジ上限/下限で環境を先に判別し、ゼロ近辺の小さな伸縮やクロスは採用しないなど、フィルターを明確化することです。
【デメリット2】パラメータ次第でノイズ過多または遅行
12/26/9を短期寄りにすると初動は捉えやすい反面、細かな上下動にも反応してダマシが増えます。
逆に期間を伸ばすと安定するもののサインは遅れがち。
まずは標準で検証し、ATRなどでボラが高い日は期間を少し長く、低い日は短くするなど、事前ルールでの微調整を徹底すると再現性が保てます。
【デメリット3】単独シグナル依存で期待値が不安定
OsMAだけのクロスや伸縮で機械的に出入りすると、時間帯やニュースで結果がブレます。
価格の押し戻り、上位足の方向、移動平均の傾きなど価格面の根拠と組み合わせ、「条件が複数そろった時だけ執行」へ落とし込むのが重要。
手数料や滑りを含めた検証と、トレード記録での改善サイクルが欠かせません。
失敗しにくい基本ルール
上位足でOsMAのゼロ位置と傾向を確認し、長期線の上下で方向を固定。
下位足では押し戻り+OsMA反転の一致を待ちましょう。
イベント直前はエントリーを控えることをおすすめします。
他インジケーターとの併用方法
移動平均線(SMA200・SMA50)×OsMA
SMA200で方向を固定(上なら買いのみ、下なら売りのみ)。SMA50を“押し目/戻り”のゾーンとして使い、価格がSMA50にリテスト→反発した足で、OsMAがゼロ上で拡大(またはマイナスからプラスへ反転)したらエントリー。損切りは直近押し安値/戻り高値の外+ATR1.5倍目安。OsMAが2~3本連続で縮小したら分割利確。
RSI × OsMA
RSI50を方向フィルターにし、上昇相場はRSI50超のときだけ買いを検討。RSIが70超を理由に即利確せず、OsMAが拡大継続なら“走る相場”と判断して保有、縮小に転じたら利確を優先。押し目狙いはRSIが40~50帯で反転し、同時にOsMAがマイナスからプラスへ切り返す局面を狙う。価格の節目(水平線)と重なれば精度が上がる。
MACD × OsMA
MACDは方向とサイクル、OsMAは勢いの強弱を見る。買いはMACDラインがゼロ上かつ上向き、同時にOsMAがプラス圏で拡大している押し目だけに限定。ブレイク直後の飛び乗りは避け、リテスト後にOsMA再拡大で入る。利確はMACDのシグナルデッドクロスまたはOsMAのピークアウト(連続縮小)で分割。双方のダイバージェンス一致は警戒サイン。
ATR × OsMA
ATRは“どれだけ逆行しても耐えるか”の設計に使う。損切りは直近スイングの外側+ATR(14)の1.2~1.8倍を目安にし、ロットは口座リスク1%以内で逆算。エントリーはOsMAの拡大再開を待ち、ATRが極端に低い(レンジ)か高すぎる(イベント直後)局面は見送り。トレーリングはATRの0.8~1.0倍で段階的に切り上げ、OsMA縮小で部分利確。
ボリンジャーバンド × OsMA
トレンド継続型は、上昇相場でミドルバンド(MA20)までの押し→反発時にOsMAがプラス再拡大でエントリー、+2σ付近でOsMAが頭打ちなら部分利確。逆張り型はレンジ上限の+2σタッチでOsMAが縮小転換、陰線確定で短期売り(下限−2σは買い)。ブレイク時はバンド拡大+OsMA拡大が揃うまで待ち、リテスト+OsMA再拡大で順張りに切り替える。
SMA/EMA:単純/指数移動平均
分割利確:ポジションの一部だけ先に利益確定する手法
RSI:買われすぎ売られすぎの指標
MACDライン:短期EMAと長期EMAの差で勢いを示す線
シグナルライン:MACDの移動平均。MACDと交差でサインを見る
デッドクロス:上向きの線が下向きの線を下抜ける現象(売りシグナルの代表)
ダイバージェンス:価格は高値更新なのに指標は更新できない等、逆行現象
リテスト待ち:ブレイク後にいったん戻るのを待ってから入るリスク低減手法
ATR:平均的な値幅(損切り幅設計に有効)
トレーリングストップ:利益方向へストップを段階的に切り上げて保護する手法
±2σ:統計的に約95%が収まる帯
ボリンジャーバンド:移動平均線の上下に標準偏差の帯(例 ±2σ)を表示
ミドルバンド:バンドの中央線(通常SMA20)
MT4・MT5・TradingViewへのOsMA導入方法
MT4/MT5
挿入→インディケータ→オシレーター→Moving Average of Oscillator。
パラメータでFast EMA 12、Slow EMA 26、Signal 9を設定。
色分けと太さを調整し、テンプレート保存。
TradingView
インジケーター→MACDを追加し、ヒストグラムをOsMAとして使用(名称がMACD Histogram)。
長さ(12/26/9)を設定、クロスやゼロ到達でアラートを作ると監視負担が減ります。
テンプレート:設定の保存
アラート:条件成立の通知
ヒストグラム表示:棒グラフでの可視化
Moving Average of Oscillator(OsMA)利用時の注意点
狭いレンジや指標発表直後はノイズが増えます。
ゼロ近辺の小さな伸縮は無視し、価格のリテスト(戻り確認)を優先。
検証と運用で期間・価格ソース・時間足を一致させること。
短期足での連打は手数料と滑りで期待値を下げやすいため、損益比と勝率の両面で評価します。
リテスト:抜けた価格帯へ戻って確認する動き
滑り(スリッページ):約定価格のズレ
価格ソース:終値や高値安値など計算基準
まとめ
Moving Average of Oscillatorは、トレンドの「方向」ではなく「勢いの加速・減速」を読み解く補助指標です。
MAで地合い、OsMAで勢い、価格の押し戻りでタイミングという分業が王道。
まずは12/26/9と上位足のゼロ位置で方向固定、下位足で押し戻り+OsMA反転を待つ基本形から始め、ATRや時間帯ルールを添えて検証・運用の一貫性を高めていきましょう。