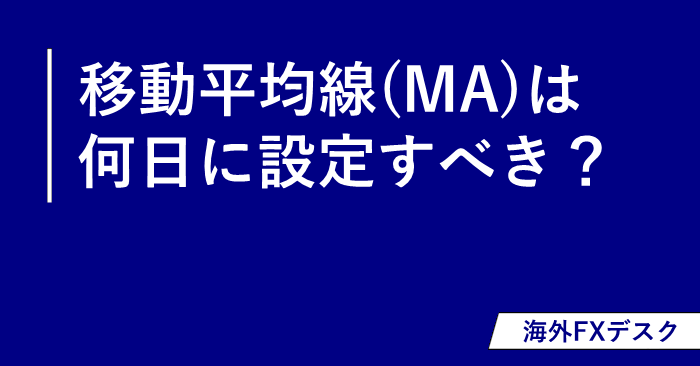多くのトレーダーが利用しているインジケーター「移動平均線(MA)」の設定期間は何日が最適なんでしょうか。
ここでは何日に設定すべきか?について、時間足別におすすめ期間を解説します。
\今ならここから登録で13000円ボーナスあり/
\元金不要で始められます/
【入力4分】XM公式
口座開設はこちら(無料)
【おすすめ選択肢】
ブランド名:FSA
口座タイプ:スタンダード
取引ツール:MT5
移動平均線は何日にすべき?基本情報
移動平均線は一定期間の終値の平均を線で可視化したテクニカル指標です。
最も一般的なのがSMA(単純移動平均)とEMA(指数平滑移動平均)で、SMAは過去の価格を等加重で平均し、EMAは直近価格に重みを置くため反応が速いのが特徴です。
インジケーター 移動平均線 何日をどう決めるかは、価格ノイズをどれだけ平滑化するかと、シグナルの遅行をどれだけ許容するかのバランス調整といえます。
よく使われる代表的な期間は、短期(5日・10日)、中期(20日・25日・50日)、長期(75日・100日・200日)。
短期ほど価格に敏感でダマシが増えやすく、長期ほどトレンド把握は安定する反面、エントリーが遅れやすくなります。用途別に使い分けるのが前提です。
初心者は「短期:5〜10」「中期:20〜25」「長期:75〜200」の基本セットから始め、銘柄や時間足のボラティリティに合わせて微調整するのが最短ルートです。
代表的な期間の意味(早見表)
| 用途 | 代表期間 | 概要 |
|---|---|---|
| 短期トレンド | 5日 / 10日 | 反応が速く、押し目・戻りの初動を捉えやすい |
| 中期トレンド | 20日 / 25日 / 50日 | ノイズと遅行のバランスが良い定番 |
| 大局トレンド | 75日 / 100日 / 200日 | 長期の方向性と節目の把握に有効 |
移動平均線(MA)には「SMA」と「EMA」があります。
次にこの2種の違いについて解説します。
SMAとEMAの違いと選び方
計算式の違いと反応速度
SMA(単純移動平均)は過去n期間の終値を等加重で平均した数値をチャートに表示します。
EMA(指数平滑移動平均)は直近のデータにより大きな重みをかけて表示します。
結果として、EMAは価格変化への反応が速く、SMAは反応が遅い代わりにノイズを抑えやすいのが特徴です。
インジケーター 移動平均線 何日を決めるとき、同じ「何日」でもEMAのほうが機敏、SMAのほうが安定と考えておきましょう。
どんな相場・手法でどちらを使うべき?
トレンド初動のキャッチや短期の押し目拾いはEMAが得意です。
ニュース後の急変動やブレイク直後などスピード重視の場面で強み。
大局の方向確認、サポート・レジスタンスの目安、持ち合い判定にはSMAが向いています。
日足や週足での中長期トレンド可視化に安定。
レンジ相場ではEMAはダマシが増えやすいため、SMAで傾きがフラットなら無理に順張りしない判断がしやすいと言えるでしょう。
短期はEMA・中長期はSMAが無難な理由
短期はエントリーと損切りの判断が秒単位で必要になるため、ラグの少ないEMAが実務的です。
中長期は「過剰反応」を避けてトレンドの骨格だけを見たいところです。
SMA25やSMA75、SMA200は多くの市場参加者が注目しやすく、効きやすい節目になりやすいと言えます。
乖離率と傾きの見方
乖離率=(価格−移動平均)/ 移動平均
短期EMAで乖離が急拡大し、同時に中期SMAとの乖離も大きいときは、利確や押し目待ちの警戒シグナルになりやすくなります。
傾きは最重要です。
移動平均が右上がりで価格がその上に位置 → 順張り優位。右下がりで価格が下 → 戻り売り優位です。
傾きが横ばいで価格が上下に抜けても戻る場合はレンジ相場です。
インジケーター 移動平均線 何日の設定を短くすると乖離と傾きの変化が大きく見えるため、トレード頻度は上がるがダマシも増えます。
まずは標準期間で基準感覚を作るのがおすすめです。
補足メモ
同じ「何日」でも市場や銘柄のボラで体感は変わります。ボラが高い銘柄は期間を少し伸ばす、ボラが低い銘柄は短くする、といった調整が有効です。バックテスト時は手数料とスリッページを必ず織り込みましょう。パラメータ最適化は過剰最適化の温床になりやすいので、検証期間と検証外期間(ウォークフォワード)を分けるといいですよ。
【時間足別】移動平均線は何日がベスト?
日足・週足・月足のおすすめ期間レンジ
日足
【短期】5日または10日。押し目・戻りの初動を追う
【中期】20日または25日、補助で50日。方向性の判定に最も使われる帯
【長期】75日、100日、200日。大局トレンドと節目の把握。日本株は25日・75日・200日が定番
使い方の目安として、価格がSMA25の上か下か、SMA75の傾きが上か下か、SMA200との位置関係で強弱を判定します。
週足
【短期】5週(約25営業日、日足25日に相当)
【中期】13週(約65日)や26週(約半年)
【長期】52週(約1年)
週足はノイズが少なく、インジケーター 移動平均線 何日の判断を安定させたいときに有効です。
月足
【中期】6か月移動平均
【長期】12か月移動平均(年足の基準)
長期投資や大循環の把握におすすめです。
日足や週足と整合しているかを確認すると精度が上がります。
デイトレ(1分/5分/15分)とスイング(4時間/日足)
1分足
【短期】EMA9/EMA21。超短期の傾きと押し戻り判定
【フィルター】SMA50 と SMA200
環境認識用に使い、順張りの方向を固定します。
5分足
【短期】EMA9/EMA20 エントリータイミングの基準
【中期】SMA50 波のリズム把握
【長期】SMA200 セッションを跨いだ地合い判断
ルール例として、価格がSMA200の上でEMA9がEMA20を上抜け、SMA50が右上がりのときのみ買いを検討などあります。
15分足
【短期】EMA10/EMA20
【中期】SMA50
【長期】SMA200
ブレイク戦略や押し目戦略に向いています。
5分足と整合が取れているか確認するとダマシが減るでしょう。
4時間足(スイング)
【短期】EMA10/EMA20
【中期】SMA50
【長期】SMA200
4時間足で方向性を決め、15分足や1時間足でタイミングをとるマルチタイムフレームが実務的です。
日足(スイング〜中期)
【短期】SMA10またはEMA10
【中期】SMA25/50
【長期】SMA200
決済は短期線割れ、追加は中期線タッチなど、線ごとに役割分担を明確にしましょう。
ボラティリティに応じた期間の伸縮ルール
基本発想
値動きが荒いときは期間を少し長くしてノイズを抑えましょう。
静かなときは期間を少し短くして機敏さを確保すると良いです。
簡易ルール例
直近の平均ボラが平常時より約30%以上高いなら、短期線を1.2〜1.3倍に延長(例 10日→12〜13日)。逆に平均ボラが約20%以上低いなら、短期線を0.8〜0.9倍に短縮(例 10日→8〜9日)。中期・長期は変えすぎない。ブレにくい基準として残すのが無難です。
ATRを使った期間微調整のコツ
ステップ
1 監視銘柄の基準ATR(例えば過去1年のATR20の平均)を記録する
2 現在のATR20が基準よりどれだけ高いか低いかを比率で見る
3 その比率に応じて短期の期間だけ微調整する
目安
ATRが基準の1.5倍なら短期期間を約1.2〜1.3倍に
ATRが基準の0.7倍なら短期期間を約0.8〜0.9倍に
注意
期間の動的変更は便利ですが、検証なしに多用すると整合が崩れます。
必ず過去検証で勝率と損益比の変化を確認しましょう。
設定時の落とし穴と対策(時間足観点の補足)
短期足だけで完結しない。方向は上位足で、タイミングは下位足で。セッションまたぎ(特にFX)のギャップや流動性低下時間帯は期間をいじるより取引そのものを控えるほうがリスクが下がるでしょう。移動平均の角度と価格位置関係が最優先。クロスだけに依存しない。
【市場別】期間の使い分け(株式・FX・仮想通貨)
日本株で定番の25日・75日・200日の意味
・25日移動平均線はおよそ1か月の営業日数に相当し、個人投資家の注目度が高い基準。押し目買い・戻り売りの目安に使いやすい。
・75日は約1四半期のトレンドを示し、景気や業績期待の変化を捉えやすい。25日との位置関係でトレンドの強弱を判断するのが実務的。
・200日は長期の方向性を映す大黒柱。価格が200日線の上にあるか下にあるかで銘柄の地合いをまず判定し、インジケーター 移動平均線 何日の短中期はその上で微調整する。
・使い方の型:価格が25日線の上、25日線が上向き、さらに75日線も上向きなら順張り有利。25日が75日を上抜ける局面は勢いが付きやすいが、決算シーズンのギャップには注意。
米国株を含む海外株の補足
・SMA50とSMA200の組み合わせが国際的に広く見られる。SMA50がSMA200を上抜けるゴールデンクロスはトレンド転換の代表的な合図として意識されやすい。
・グロース株などボラが高い銘柄はEMA20やEMA50で機動力を確保しつつ、SMA200で大枠の方向を固定するやり方が実務的。
FXで機能しやすい期間とセッション特性
・短期の方向取りはEMA重視が便利。例として、M5やM15ではEMA9/EMA20、H1やH4ではEMA10/EMA20が使いやすい。環境認識にはSMA50とSMA200を併置しておく。
・東京時間はレンジになりやすく、インジケーター 移動平均線 何日の短期設定だけで追うとダマシが増える。ロンドン突入後に傾きが出てからトレードするなど時間帯の使い分けが有効。
・通貨ペア特性の例:ポンド系はボラが大きく、短期期間を少し伸ばす(例 9→12、20→24)とノイズ低減に役立つ。ドル円は比較的トレンドが素直な時間帯があり、EMA20とSMA50の組み合わせが扱いやすい。
・1日の地合い判断はSMA200の上下、タイミングはEMA9とEMA20のクロスと価格の乖離で、という役割分担がシンプルで失敗しにくい。
仮想通貨(暗号資産)での設定と注意点
・24時間365日動くため日足の「クローズ」が相対的。短期の勢い把握はEMAが有利で、EMA20やEMA50が定番。強いトレンドではEMA20にタッチした押し目がワークしやすい。
・中長期はSMA200(日足)で大局を確認。加えて週足のEMA20やSMA50を併用すると相場のサイクル感が掴みやすい。
・ビットコインの実務的セット例:4時間足でEMA20/EMA50/EMA200、日足でSMA50/SMA200。価格が日足SMA200の上で、4時間足EMA20が上向きのときのみ順張り、などのフィルタが機能しやすい。
・注意点として、急騰急落が多く乖離が極端になりやすい。インジケーター 移動平均線 何日の短期設定をそのまま維持せず、ボラが高い局面は期間を少し延ばしてノイズを抑えると良い。
全銘柄共通の考え方(市場をまたいで通用するルール)
・長期線(SMA200など)で地合いを固定し、中期線(SMA50やSMA25)で波の把握、短期線(EMA9/EMA20など)でタイミングを取る三層構造が基本。
・クロスだけに依存しない。最優先は移動平均線の傾きと価格の位置関係。傾きがフラットなら「無理にやらない」を選べるのが上達の近道。
・検証は必ず時間足別・銘柄別に行い、手数料とスリッページを織り込む。過剰最適化は避け、標準期間からの微調整で十分に戦える。
シグナルの活用方法(クロス・傾き・グランビル)
ゴールデンクロス/デッドクロスの精度を上げる条件
・長期線の位置と傾きが最優先。価格と短期線がSMA200の上にあり、SMA200自体が上向きのときのゴールデンクロスは勝ちやすい。逆にSMA200の下かつ下向きのときのデッドクロスが信頼度高め。
・クロスする移動平均の角度がそろっていること。短期も中期も上向きの中で上抜けるクロスは継続性が出やすい。片方だけが立っている「尖りクロス」は一過性になりがち。
・過度な乖離の後のクロスは見送り。急騰直後に短期が中期を追い越すクロスは利確売りに飲まれやすい。冷却後のクロスを待つ。
・ボラティリティの安定。ATRが直近高水準だとノイズも大きい。インジケーター 移動平均線 何日の短期期間を少し延ばす、もしくはクロス後の押し戻り確認を入れるとダマシが減る。
・出来高の裏付け(株式)。上昇クロス時に出来高増なら信頼度アップ。FXはティックボリュームやセッション切り替えの時間帯(ロンドン開始など)を代替指標にする。
エントリーと損切り・利確の型(例)
・買い例:日足で価格がSMA200上、SMA50上向き。短期EMA10がSMA20を上抜けたら、直近の押し安値下に損切り。利確は前回高値手前、またはEMA10割れで一部利食い。
・売り例:価格がSMA200下、SMA50下向き。EMA10がSMA20を下抜け。損切りは直近戻り高値の上。利確は前回安値手前、またはEMA10上抜けで分割決済。
パーフェクトオーダーの判定と崩れの兆し
・上昇の理想配列は短期>中期>長期で全て右上がり(例:EMA10>SMA25>SMA75>SMA200)。下降は逆。
・維持のコツは「距離」と「傾き」。移動平均同士の間隔が適度に開いたまま傾きが保たれている間は押し目が機能しやすい。間隔が詰まり始めたら勢いの低下。
・崩れの初期サインは、短期が中期に食い込む、価格が中期線で止まらず貫通する、短期の高値更新に対してオシレーターが高値を更新できない(ダイバージェンス)など。
・運用の型:パーフェクトオーダー中は短期線タッチでの押し目買い(売り)に徹し、配列が崩れ始めたら新規は控えて保有分の利確を優先。
グランビルの法則の実用化
【買いが有利な局面】
1 上向きの移動平均(例:SMA25)を価格が上抜けた直後。
2 上向きの移動平均に価格が戻ってきて反発したとき(押し目)。
【売りが有利な局面】
1 下向きの移動平均を価格が下抜けた直後。
2 下向きの移動平均に戻って反落したとき(戻り売り)。
インジケーター 移動平均線 何日の基準としては、短中期はSMA25やEMA20、トレンドの土台はSMA75やSMA200が扱いやすい。短期はEMA20、押し目確認はSMA25、環境認識はSMA200の三段構えが実務的。
チェックリスト(エントリー前に確認)
・価格は長期線(SMA200)の上か下か
・長期線と中期線の傾きは整合しているか
・クロスは過度な乖離の直後ではないか
・直近の高安値や水平線と衝突していないか
・イベントやセッション切替の直前ではないか
・損切り位置と想定利確位置を先に決め、損益比が1対1.5以上確保できるか
ミニケーススタディ(買い)
・前提:日足で価格がSMA200とSMA50の上、SMA50は上向き。短期EMA10がSMA20を上抜け、出来高増。
・行動:押し目待ちで前回ブレイク水準へのリテストを待ち、反発確認でエントリー。損切りは押し安値の少し下。
・管理:EMA10割れで半分利確、残りはSMA20割れで全利確。強いときは前回高値更新ごとにストップを切り上げる。
・ポイント:クロスだけで飛び乗らず「押し目確認」を入れると勝率が安定する。
ミニケーススタディ(売り)
・前提:4時間足で価格がSMA200下、SMA50下向き。EMA10がSMA20を下抜け、ロンドン時間でボラ拡大。
・行動:戻り売り。直近のサポート割れ後のリテストで反落確認。損切りは戻り高値上。
・管理:EMA10上抜けで分割利確、節目到達で残りを利確。
・ポイント:セッションの変わり目を味方にし、インジケーター 移動平均線 何日の短期はEMAで機動力を確保。
移動平均線のおすすめ期間セット例
目的別おすすめセット(順張り・逆張り・持ち合い判定)
・順張り(トレンドフォロー)
短期 EMA9/EMA21+中期 SMA50+長期 SMA200
使い方:価格がSMA200の上で、SMA50が上向きのときのみ買い検討。EMA9がEMA21を上抜け、押し目で前回高値の手前までを第一目標。インジケーター 移動平均線 何日の短期は9と21で機動力を確保。
・逆張り(短期の押し目・戻り狙い)
短期 SMA10 or EMA10+中期 SMA20/25
使い方:上昇トレンド中に価格がSMA10を割ってSMA20/25で反発したら小ロットで押し目買い。下降なら逆。環境認識としてSMA200の上下で方向を固定。
・持ち合い(レンジ判定)
SMA25とSMA75を併置、必要に応じてSMA200
判定基準:SMA25とSMA75の傾きがほぼフラット、価格が両線を頻繁にまたぐ、移動平均間の距離が縮む。レンジ中はブレイク確定まで順張り新規を控える。
期間の組み合わせリスト(時間軸別の定番)
・スキャル(1分)
EMA9/EMA21、SMA50、SMA200
・デイトレ(5分)
EMA9/EMA20、SMA50、SMA200
・短期回転(15分)
EMA10/EMA20、SMA50、SMA200
・スイング(4時間)
EMA10/EMA20、SMA50、SMA200
・中期(日足)
SMA10 or EMA10、SMA25/50、SMA200
・長期(週足)
SMA13週、SMA26週、SMA52週
シンプル運用ルール例
・買い
条件:価格がSMA200の上、SMA50上向き、EMA9がEMA20を上抜け
エントリー:ブレイク後の戻りを待って直近レジスタンスの裏で反発確認
損切り:直近押し安値の下
利確:前回高値手前で分割、EMA9割れで残り処分
・売り
条件:価格がSMA200の下、SMA50下向き、EMA9がEMA20を下抜け
エントリー:サポート割れの戻りを待って反落確認
損切り:直近戻り高値の上
利確:前回安値手前とEMA9上抜けで分割
検証チェックリスト(過剰最適化を避ける)
- データ分割:インサンプル(調整用)とアウトオブサンプル(検証用)を分ける。可能ならウォークフォワードで時系列に沿って評価する。
- 取引コスト:手数料とスリッページを必ず反映。スキャルや短期は結果が大きく変わる。
- 指標の一貫性:インジケーター 移動平均線 何日のパラメータを1〜2だけ動かしても成績が大きく崩れないか確認。尖った最適点は避ける。
- レジーム別検証:トレンド相場、レンジ相場、ボラ高・低の期間ごとに勝率と損益比、ドローダウンを確認。
- 指標過多の回避:移動平均は最大3〜4本まで。情報過多は判断遅延と矛盾を生む。
- 損益比の基準:勝率よりも期待値。最低でも損益比1対1.5、理想は1対2を目指す。
- ロットと連敗耐性:最大想定連敗数に基づくロット設計。ドローダウン20%以内を目標に。
- 実運用前の紙トレード:最低20〜30トレードを手で記録し、ルール通りに執行できるかを確認。
ここまでのQ&A
Q. 結局、移動平均線は何日にすべき?
A. 標準は短期9〜10、中期20〜25、長期50と200。これを基準に、銘柄のボラや時間足に合わせて微調整するのが現実的。
【プラットフォーム別】期間設定の方法
MT4/MT5でSMA/EMAと「期間」を設定する手順
- 挿入 → インディケータ → トレンド → Moving Average を選ぶ(またはチャート上で右クリック → 表示中のインディケータ → 追加)。
- パラメータを設定する。
・期間(Period):インジケーター 移動平均線 何日の「何日」に相当。例 10、25、50、200 など。
・種別(MA method):SMA(単純)、EMA(指数)、Smoothed(平滑)、Linear Weighted(加重)。短期はEMA、中長期はSMAが無難。
・適用価格(Apply to):Close(終値)を基本。Open/High/Low、Median(HL/2)、Typical(HLC/3)、Weighted(HLCC/4)なども選べる。検証の再現性を保つなら終値固定を推奨。
・シフト(Shift):表示位置を右や左へずらす。通常は0のまま。
・色・太さ・スタイル:短期を暖色、中期を中間色、長期を寒色にすると視認性が上がる。 - OK を押してチャートに表示。複数本使う場合は同手順で本数分追加。
- よく使う組み合わせはテンプレートに保存(チャート上で右クリック → テンプレート → 名前を付けて保存)。別銘柄でも同じ設定をすぐ呼び出せる。
おまけ
・ナビゲータの「Moving Average」をチャートへドラッグすると素早く追加できる。
・時間足を切り替えても期間は「本数」基準で解釈される(例:5分足の20=100分、1時間足の20=20時間)。この認識違いが多いので注意。
・Heikin Ashi(平均足)チャートに移動平均を重ねると値が変わる。通常ローソク足で検証した設定は通常ローソク足で使う。
TradingViewでの設定手順
- 画面上部「インジケーター」をクリックし、Moving Average(SMA)や Exponential Moving Average(EMA)を追加。検索窓に「MA」「EMA」と入力すると出てくる。
- インジケーターの設定(歯車アイコン)で以下を調整。
・Length(期間):インジケーター 移動平均線 何日の基準。例 10、25、50、200。
・Source(基準価格):Closeを基本。Open/High/Low/HL2/HLC3/HLCC4 なども選択可能。
・Offset(オフセット):線を視覚的にずらす機能。通常は0。
・Style:色、太さ、ラインタイプを変更。短中長の色分けを統一しておく。 - 同じチャートに複数本を追加して色分け。
- 現在の構成をインジケーターテンプレートとして保存(インジケータ設定のドロップダウン、またはチャートのテンプレート機能から保存)。
- アラート活用例:移動平均線のクロスで通知。アラート → 条件で「指標の交差(Crossing)」を選び、短期MAと中期MAを指定。執行の見逃しを減らせる。
よくある設定ミス(プラットフォーム共通)
・期間の単位を誤解している
「20」は常に今の時間足での20本。時間足を変えると意味合いが別物になる。
・SMAとEMAを無意識に混在
以前の検証はSMAなのに、実運用でEMAに変えて結果が合わない、など。必ず明記して統一。
・Apply to(基準価格)がバラバラ
片方がClose、片方がHLC3などになるとクロス条件がズレる。基本は終値で統一。
・シフトやオフセットが0でない
表示が未来方向にずれて見えると判断ミスの元。常に0で確認。
・色分けが不明瞭
短中長の識別が瞬時にできないと執行が遅れる。色と太さで役割を固定。
・検証と実運用の環境差
平均足に切り替えた、対数スケールにした、レイアウトの時間足が違う、などの小さな差が結果を変える。テンプレートで環境を固定する。
運用のチェックポイント
・長期(例 200)で地合い、 中期(例 50/25)で波、 短期(例 9/10/20)でタイミングという役割分担を常に意識。
・時間足は上位で方向、下位でタイミング。
・アラートや色分けで判断コストを下げ、再現可能なルールに落とし込む。
移動平均線の期間設定でよくある失敗と回避方法
・「万能の何日」を探してしまう
どの市場・銘柄・時間足でも通用する“最強期間”は存在しない。
対策:標準(短期9〜10、中期20〜25、長期50・200)を起点に、対象のボラティリティと時間足で微調整。検証して根拠を持つ。
・クロスだけで機械的にエントリー
短期と中期のクロスはノイズで頻発しやすい。
対策:長期線の傾きと位置(価格が長期線の上下どちらか)を必ずフィルターに。ブレイク後の戻り確認など一手間を挟む。
・上位足を無視する
下位足で上向きでも、上位足が下向きだと逆行しやすい。
対策:上位足で方向、下位足でタイミングの原則。最低でも二つの時間足で整合を確認。
・ボラティリティを考慮しない
急騰急落局面で短期期間のまま追うとダマシ増。
対策:ATRなどでボラを把握し、短期期間を少し延ばす(例 10→12〜13)などの調整を事前ルール化。
・過剰最適化(カーブフィッティング)
過去の一部期間だけ良いパラメータに寄せると実運用で崩れる。
対策:インサンプルとアウトサンプルを分け、ウォークフォワードで確認。期間は整数か一般的な値に留め、尖った最適点を避ける。
・コストとスリッページを無視
特に短期は手数料・滑りで成績が激変。
対策:検証に必ず反映。想定損益比はコスト込みで1対1.5以上を基準。
・基準価格の不一致(CloseとHLC3など)
同じ条件でも線の位置がズレて再現性が落ちる。
対策:基本は終値で統一。検証と運用で設定を揃える。
・SMAとEMAを混在させて検証結果が再現不能
検証はSMA、運用でEMAに切り替えて別物になる例が多い。
対策:各線の種別を明記して固定。短期EMA・中長期SMAなど役割分担を設計に落とす。
・線を引きすぎて判断麻痺
5本以上並べると矛盾が増える。
対策:短期・中期・長期の3〜4本で十分。役割を明確にして余計な線は削る。
・イベントや時間帯の特性を無視
指標直前や流動性が薄い時間帯にダマシ多発。
対策:取引禁止時間帯を事前に決める。FXはロンドン開始やNYオープン前後の特性を理解する。
・アラート未活用で見逃しや飛び乗り
常時監視できず質が落ちる。
対策:クロスや価格×移動平均のタッチにアラート設定。押し戻り確認のトリガーに。
・ロットと損切りが期間に合っていない
短期設定で損切りが近すぎ連発、長期設定で損切りが遠すぎリスクリワード悪化。
対策:損切りを直近の押し安値・戻り高値の外側に置き、期待値が確保できるロットへ調整。
・移動平均を“絶対の壁”と誤解
線タッチ=反転と決め打ちして逆張り乱発。
対策:線は目安。ローソク足の反転サイン、出来高(株)、上位足の傾きで裏付けを。
・時間足切替で意味が変わるのを忘れる
5分の20と1時間の20は別物。
対策:期間は“本数”。時間足が変われば意味も変わる前提でルールを設計。
移動平均線は何日にすべき?決め方まとめ
- 目的を決める(順張りで波に乗るのか、押し戻りを拾うのか、レンジ回避か)
- 取引時間軸を確定(スキャル、デイトレ、スイング、投資)
- 標準プリセットを適用(短期9〜10、中期20〜25、長期50・200。短期はEMA、中長期はSMAが無難)
- 相場状態で微調整(ATRや最近の値幅で短期だけ±20〜30%の範囲で調整)
- 検証(インサンプル調整→アウトサンプル確認→必要なら軽く再調整)
- 実運用(アラート設定、執行ルール、損切り・利確と分割の基準を明文化)
- 定期見直し(月次で勝率・損益比・最大DDを点検。大きな崩れがなければ期間はいじらない)
用途別の最初の一歩(例)
・株式(日足)
短期 EMA10、中期 SMA25/50、長期 SMA200
・FX(5分〜1時間)
短期 EMA9/EMA20、中期 SMA50、長期 SMA200
・仮想通貨(4時間〜日足)
短期 EMA20/EMA50、中期 SMA50、長期 SMA200
最後の指針
・傾きと位置関係が“最優先”。クロスは補助。
・検証と運用の設定を一致させる。
・「やらない」という選択肢を持つ。レンジやイベント前は見送ることで資金が守れる。
移動平均線(MA)のセット手順
【MT4/MT5での移動平均線のセット手順】
手順リスト
- チャートを開く
- 上部メニューの「挿入(Insert)」をクリック
- 「インディケーター」→「トレンド」→「Moving Average」を選択
- パラメーター(期間や種別)を設定
- 線の色や太さなどスタイルを調整
- 「OK」で適用完了
解説
- 期間:短期なら「5」や「20」、中期「50」、長期「100」や「200」が一般的です。
- 種別:Simple(単純移動平均:SMA)かExponential(指数平滑移動平均:EMA)を選べます。
- 適用価格:通常は「Close(終値)」が使用されます。
【TradingViewでの移動平均線のセット手順】
手順リスト
- チャートを表示
- 上部の「インジケーター」アイコンをクリック
- 検索窓に「Moving Average」または「EMA」と入力
- 表示されたインジケーターをクリックで追加
- チャート左上の「設定(歯車アイコン)」からパラメーターやスタイルを変更
解説
- 複数のMAを同時に表示して、ゴールデンクロスやデッドクロスの確認にも活用可能。
- SMAやEMAの違いを理解して使い分けると、より精度の高い分析ができます。
まとめ
移動平均線の「何日」に絶対解はありません。
まずは短期9〜10・中期20〜25・長期50/200(短期はEMA、中長期はSMA)を基準に、銘柄や時間足のボラで±20〜30%を微調整しましょう。
上位足で方向、下位足でタイミング。最優先は線の傾きと価格位置で、クロスは補助に留めておきましょう。
SMA200の上下で地合いを固定し、手数料・滑りを含めて検証。
設定(種別・適用価格)は運用と一致させ、アラート活用とルールの文書化で継続検証をしていきましょう。