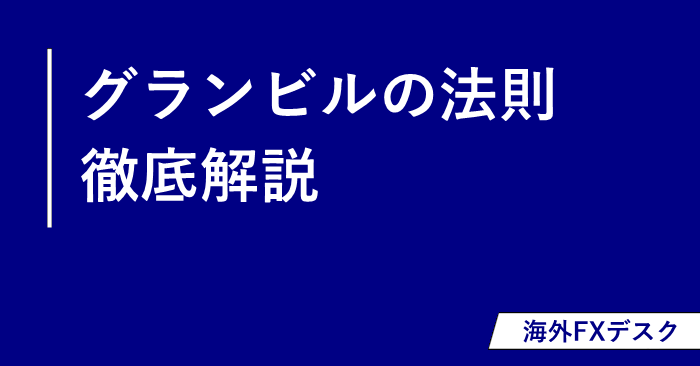勝ち続けているFXトレーダーの多くが意識しテクニカル分析に取り入れている「グランビルの法則」。
ここではグランビルの法則とはどんなものなのか?基本情報や使い方をまとめました。
\今ならここから登録で13000円ボーナスあり/
\元金不要で始められます/
【入力4分】XM公式
口座開設はこちら(無料)
【おすすめ選択肢】
ブランド名:FSA
口座タイプ:スタンダード
取引ツール:MT5
グランビルの法則とは?
グランビルの法則とは、移動平均線と価格の関係性をもとに売買シグナルを判断するテクニカル分析の理論です。
1960年代にアメリカの投資評論家ジョセフ・グランビルによって提唱され、株式や為替、仮想通貨など幅広いマーケットで活用されています。
この法則の魅力は、シンプルで視覚的にわかりやすく、初心者でもすぐに実践しやすい点です。
チャート上に移動平均線を引き、ローソク足の位置や方向性から「今は買うべきか、売るべきか」を見極めるルールが整理されています。
特にFXのようなトレンドが生まれやすい市場では、グランビルの法則は非常に有効です。
移動平均線の上抜け・下抜け、乖離からの戻り、傾きの変化など、8つの売買タイミングを理解することで、トレードの精度が格段に向上します。
このセクションでは、まずグランビルの法則の成り立ちと基本的な構造をわかりやすく解説していきます。
提唱者ジョセフ・グランビルとは
グランビルの法則を提唱したジョセフ・E・グランビル(Joseph E. Granville)は、アメリカの著名な投資評論家・テクニカルアナリストです。
彼は1963年に出版した著書『Granville’s New Key to Stock Market Profits』の中で、この理論を体系化しました。
彼の分析スタイルは、ファンダメンタルズではなくチャート重視。
特に「移動平均線」に注目し、価格との関係性から売買タイミングを定義したのが画期的でした。
その手法は、シンプルで実践的なテクニカル理論として、今でも多くの投資家に支持されています。
また、彼はメディアでも「大胆な発言」と「派手なプレゼン」で有名でした。
チャートだけでなく、市場心理や群集心理にも着目した分析を行っていた点でも注目されます。
FXや株の世界で「テクニカル分析」という考え方が一般化した背景には、こうした先駆者たちの功績があるのです。
グランビルの法則の基本構造
グランビルの法則は、移動平均線(Moving Average)と価格の動きから売買のタイミングを判断する8つのシグナルで構成されています。
この法則の軸となるのは、主に「長期移動平均線(例:200MA)」です。
この8つのシグナルは、買いシグナルが4つ、売りシグナルが4つに分かれており、トレンドの転換点や継続中の押し目・戻りを狙うために活用されます。
構造としては以下のような要素を見ます。
- 価格が移動平均線を上抜けるか下抜けるか
- 移動平均線の傾きが上向きか下向きか
- 価格と移動平均線の乖離がどの程度あるか
このような視点から、価格の動きを冷静に分析することで、相場の転換点を先読みしたり、継続するトレンドにうまく乗ることができるのです。
グランビルの法則は機械的に判断しやすいため、感情に左右されにくいトレードスタイルを築きたい人にも向いています。
移動平均線(MA)との関係性とは?
グランビルの法則の根幹にあるのが、移動平均線(Moving Average:MA)と価格の位置関係です。
移動平均線とは、一定期間の価格の平均値を線でつないだもので、相場の流れ(トレンド)を視覚的に捉える指標として広く使われています。
MAは滑らかでわかりやすく、短期・中期・長期と期間を変えることで、異なる時間軸でのトレンドを把握できます。
グランビルの法則では、主に「長期MA」(例:200日移動平均線)が使われることが多いです。
このMAに対して、現在の価格が「上にあるのか」「下にあるのか」「抜けたのか」「乖離しすぎているのか」といった相対的な位置を分析し、売買シグナルを判断します。
例えば、価格がMAを上に抜けた場合は「上昇トレンドの始まり」と判断されることがあり、逆にMAを下抜ければ「下落トレンドの可能性」と見なされます。
MAの角度(上向き/下向き)も重要な判断材料です。
このように、MAはグランビルの法則において「相場の体温計」のような役割を果たし、価格との動きのズレから売買のヒントを得るツールとなるのです。
グランビルの法則 8つのシグナル解説
グランビルの法則の最大の特徴は、8つの明確な売買シグナルに基づいて相場のタイミングを判断できることです。
この8つのシグナルは、トレンド転換や押し目、戻りといった重要な局面を捉えるための指針となり、特に初心者がエントリーとエグジットのタイミングに悩んだときの「道しるべ」になります。
シグナルは以下のように分類されます。
- 買いシグナル(No.1〜4)
- 新たな上昇トレンドのスタート
- 押し目買い
- 買い増し
- 一時的な反発狙い
- 売りシグナル(No.5〜8)
- 新たな下落トレンドのスタート
- 戻り売り
- 売り増し
- 一時的な反落狙い
これらはすべて「価格と移動平均線の関係」から読み取れるもので、視覚的に判断しやすいのも特徴です。
また、シグナルはチャートを読む力の強化にもつながるため、繰り返し確認することで相場観を育てることができます。
買いシグナル
グランビルの法則における「買いシグナル」は、価格が移動平均線よりも下にあった状態から上昇に転じる場面や、上昇トレンド中の押し目などを捉えるサインです。
以下の4パターンがあります。
買いシグナル1:上抜けによるトレンド転換
価格が下落から反転し、横ばい~上向きになった移動平均線を下から上に突き抜けたときに出るシグナルです。
新たな上昇トレンドの始まりを示唆します。
買いシグナル2:押し目買い
上昇トレンド中に、一時的に価格が下落して移動平均線に接近し、その後再び反発したとき。
移動平均線が上向きであることが前提条件です。
買いシグナル3:買い増しタイミング
価格が移動平均線の上にあり、再びMAに近づいたあと、タッチせずに上昇した場合。
強いトレンド継続の可能性を示します。
買いシグナル4:乖離による一時的な反発狙い
移動平均線が下向きであっても、価格が移動平均線から大きく乖離して急落した後に、反発の兆しを見せる場面で現れます。
逆張り的なエントリーです。
これらの買いシグナルは、順張りと逆張りの両方に対応しており、状況に応じて柔軟に活用できます。
ただし、すべてのシグナルが有効に働くわけではないため、他の指標やチャートパターンと併用するとより効果的です。
売りシグナル
グランビルの法則における「売りシグナル」は、価格が移動平均線を下回り始めた場面や、下落トレンド中の戻りを捉えるタイミングで活用されます。
売りの判断材料として、以下の4パターンが定義されています。
売りシグナル1:下抜けによるトレンド転換
価格が上昇していた状態から反転し、横ばい~下向きの移動平均線を上から下に抜けたときに出るシグナルです。
下降トレンドの始まりを示す非常に重要な局面です。
売りシグナル2:戻り売り
下落トレンド中に価格が一時的に上昇し、移動平均線まで戻ってきたが、再び下落した場合に出現。
MAは下向きのままである必要があります。
売りシグナル3:売り増しタイミング
価格が移動平均線の下にある状態で、一度MAに接近するもタッチせずに下落再開した場合です。
トレンドの勢いが継続するサインと見なされます。
売りシグナル4:乖離による一時的な反落狙い
上昇トレンド中であっても、価格が移動平均線から大きく乖離して急上昇した後、一時的な反落を狙う逆張り的な売りポイントです。
MAが上向きのままでも成立します。
これらの売りシグナルも、買いシグナル同様に「順張り」「逆張り」の両方に使えます。
ただし、特に逆張り系のシグナル(シグナル4・8)は、トレンドの強さや相場環境を見誤ると損失に繋がりやすいため注意が必要です。
買い・売りシグナルを使う際の注意点
グランビルの法則は非常に有用なテクニカル手法ですが、そのまま鵜呑みにして使うと失敗するリスクもあります。
ここでは、初心者が特に意識すべき注意点を整理しておきます。
1. ダマシ(フェイクシグナル)の存在
価格が移動平均線を抜けたとしても、それが一時的な値動きで終わり、すぐに元に戻るケース(ダマシ)は珍しくありません。
シグナルが出たからといって即エントリーせず、出来高やローソク足の形、他のインジケーターで裏付けを取ることが重要です。
2. 時間足による精度の差
短期足(5分足や15分足など)でグランビルの法則を使うと、ノイズが多く、信頼性が落ちる傾向があります。
初心者にはまず日足や4時間足で使うことを推奨します。
3. 他のテクニカル指標との併用が基本
グランビルの法則だけで勝ち続けるのは難しいです。
MACD・RSI・ボリンジャーバンド・水平線など、他のツールと組み合わせることで、シグナルの精度が高まります。
4. トレンド環境を誤認しない
グランビルの法則はトレンド相場で特に有効ですが、レンジ相場では多くのダマシが発生します。
まずは「トレンドが出ているかどうか」を判断する習慣をつけましょう。
こうした注意点を押さえることで、グランビルの法則は再現性のある武器として機能し始めます。
ルールを盲信するのではなく、状況を見て“選んで使う”という姿勢が大切です。
FXトレードでの活用方法
グランビルの法則は、もともとは株式市場向けに考案されたものですが、トレンドの出やすいFX相場に非常に適している分析手法です。
特に移動平均線の動きが素直に表れやすい通貨ペア(例:ドル円・ユーロドルなど)で有効性が高まります。
ここでは、FXトレーダーがグランビルの法則を活用する上での具体的なポイントやコツを解説します。
単に知識として覚えるのではなく、自分のトレードに取り入れて利益を伸ばすための実践的な考え方が中心です。
まず基本となるのは、「どの期間の移動平均線を使うか」「どの時間軸で見るか」「どうやってシグナルの信頼度を高めるか」といった設定の部分です。
次のセクションではそれぞれのポイントを順に掘り下げていきましょう。
移動平均線の期間設定
グランビルの法則をFXで使う際に最も重要なポイントのひとつが、移動平均線(MA)の期間設定です。
特に初心者におすすめなのが、200期間の移動平均線(200MA)です。
なぜ200MAなのか?
200MAは、相場参加者の多くが注目している長期トレンドの目安であり、機関投資家やプロトレーダーも意識するラインです。
価格が200MAを上抜けたり下抜けたりすると、市場心理に大きな影響を与える傾向があります。
その他の代表的な期間設定
| 種類 | 特徴・使いどころ |
|---|---|
| 20MA(短期) | 短期的な押し目や戻りの判断に有効 |
| 50MA(中期) | 中期トレンドの強さ確認に使われることが多い |
| 200MA(長期) | グランビル法則の判断基準に最適 |
私個人としては、20MAを使っています。
各時間足に20MAをセットし、1時間足チャートには4時間足の20MAとなる80MA、日足の20MAとなる480MAも同時に表示させ、それぞれのMA同士がグランビルの法則になるタイミングを狙う手法を採用しています。
同じように4時間足チャートには、日足の20MAと同じとなる120MA、週足の20MAとなる600MAを同時に表示させています。
単純移動平均(SMA) vs 指数平滑移動平均(EMA)
グランビルの法則では、SMA(単純移動平均)が一般的に用いられます。
より価格の反応を敏感に捉えたい場合は、EMA(指数移動平均)を補助的に使うのも手です。
結論としては、「まずは200SMAをベースにチャートを見てみること」がFX初心者にとっては最も安全かつ学びやすいアプローチです。
時間軸別の使い方(4時間足・日足など)
グランビルの法則をFXで使う際に見落としがちなポイントが「時間軸の選び方」です。
移動平均線のシグナルは、使う時間足によって“効き方”が大きく変わるため、初心者は特に注意が必要です。
初心者におすすめの時間足
| 時間足 | 特徴・活用法 |
|---|---|
| 日足(D1) | ダマシが少なく、信頼性が高い |
| 4時間足(H4) | エントリーの精度を高めやすい |
| 1時間足(H1) | 短期トレード向け。要フィルター |
初心者はまず日足でトレンドの方向を確認し、4時間足でシグナルを見るという「複数時間足分析(マルチタイムフレーム分析)」が基本です。
なぜ短期足(5分足・15分足)は避けるべきか?
短期足はノイズが多く、グランビルの売買シグナルも“ダマシ”が頻発しやすくなります。
特に移動平均線が横ばいになりやすく、シグナルの有効性が下がる傾向があるため、経験者向きです。
トレンドの流れを「時間足ごとに統一」すること
日足で上昇トレンド中に、4時間足でも買いシグナルが出ている──このように時間軸ごとの方向性が一致した場面こそ、高勝率なエントリーチャンスです。
まずは「日足で全体の流れを把握 → 4時間足でタイミングを取る」の流れを意識して、無理のないトレードを心がけましょう。
トレード手法への組み込み方
グランビルの法則は、単体でも有効ですが、既存のトレード手法に“補助ツール”として組み込むことで、精度や安定性が大きく向上します。
ここでは、FX初心者でも取り入れやすい実践的な組み方を紹介します。
エントリーのタイミング調整に使う
例えば、「水平線」や「チャートパターン」などで大まかなエントリーポイントを決めた後に、グランビルの買い・売りシグナルが出ているかを確認する使い方が有効です。
「根拠が1つより2つあれば、信頼度が高まる」という考え方です。
決済判断にも使える
「MAから大きく乖離している=反転の可能性がある」といったシグナル4や8を使えば、利確や損切りの判断にも役立ちます。
特に利確が苦手な初心者は、「移動平均線からの距離」を指標にすると、利益を確保しやすくなります。
資金管理ルールとセットで考える
グランビルの法則はトレードの“タイミング”を教えてくれますが、リスク管理まではしてくれません。
エントリー時には、ロット管理や損切りラインを明確に設定しておきましょう。
手法に取り入れるときのコツは「メインで使うのか、補助として使うのか」を自分で明確に決めることです。
中途半端に使うと迷いやすくなるので、ルール化・検証を繰り返すことが成功の鍵です。
RSIやMACDとの併用例
グランビルの法則のシグナルはシンプルで分かりやすい一方、「トレンドの強さ」や「相場の勢い」を判断するには少し情報が足りないこともあります。
そんな時に役立つのが、RSI(相対力指数)やMACD(移動平均収束拡散法)との併用です。
RSI(Relative Strength Index)
RSIは、相場の「買われすぎ・売られすぎ」を数値化したオシレーター系指標です。
- RSIが30以下で買いシグナル(グランビル1)が出れば、反転の信頼度が高まる
- RSIが70以上で売りシグナル(グランビル5や8)が出た場合も同様
→ 逆張り型のシグナル4・8と特に相性が良いです。
MACD(Moving Average Convergence Divergence)
MACDは、トレンドの方向と勢いを判断できる指標で、移動平均線との親和性が高いです。
- MACDがゴールデンクロス中にグランビルの買いシグナル
- MACDがデッドクロス中にグランビルの売りシグナル
→ トレンド型シグナル(1・2・5・6)との組み合わせでエントリーの精度UP。
補足:複数指標の“重ねすぎ”に注意
指標を増やせば増やすほど、「シグナルが揃うまで動けない」状態になりがちです。
最初はグランビル+1指標(RSIかMACD)くらいから始めるのがベストです。
これらの補助指標をうまく活用することで、グランビルの法則の“判断の確度”を格段に高めることができます。
ダウ理論との組み合わせ活用
グランビルの法則と並んで、FXの世界で非常に有名な理論が「ダウ理論」です。
この2つの理論はそれぞれ独立した分析法ですが、組み合わせることでトレンド判断の精度が飛躍的に向上します。
ダウ理論は、「高値・安値の切り上げ・切り下げ」によってトレンドを定義する理論で、グランビルのような移動平均線ではなく、「価格の波形」を見る点が特徴です。
一方、グランビルの法則は「価格と移動平均線の関係性」から売買判断を行います。
この2つを組み合わせることで、トレンドの発生・継続・転換を多角的に判断できるようになります。
次のセクションでは、具体的にどのように連携させて使うかを見ていきましょう。
トレンド判断におけるフィルターとして
グランビルの法則は移動平均線の動きをもとにシグナルを出しますが、必ずしもそのシグナルが「今のトレンドと合っている」とは限りません。
そこで活躍するのがダウ理論の“波形分析”によるトレンド確認です。
組み合わせ方の基本
- ダウ理論でトレンドを判断
- 上昇トレンド:高値・安値ともに切り上げ
- 下降トレンド:高値・安値ともに切り下げ
- グランビルでエントリーポイントを探す
- 上昇トレンド中に「グランビルの買いシグナル(2または3)」が出れば押し目買い
- 下降トレンド中に「グランビルの売りシグナル(6または7)」が出れば戻り売り
フィルターとして使うことで“無駄なエントリー”を減らせる
例えば、ダウ理論的にはまだ下降トレンドが継続中なのに、グランビルで買いシグナルが出ていたとします。
この場合は買いを見送る判断ができるため、「負けトレードを減らすフィルター」として非常に有効です。
トレンドの“質”を見極める習慣を
移動平均線の傾きだけでなく、波の形(安値・高値の位置関係)をセットで観察することで、相場の本質的な流れがよりクリアに見えてきます。
「グランビル=タイミング」「ダウ理論=方向性」──この2軸で判断するのが、勝率と再現性の高いトレード戦略の鍵です。
「波形+MA」の組み合わせパターン
グランビルの法則とダウ理論を組み合わせる際、最も活用しやすいのが“波形+移動平均線”によるトレンド分析のパターン化です。
ここでは、実際のチャートでよく見られるパターンと、それに対する売買判断の組み立て方を紹介します。
上昇トレンドの基本パターン
- 高値・安値がともに切り上がっている(ダウ理論)
- 価格が移動平均線の上に位置(グランビル)
- MAは上向きに推移
この場合、**押し目をつけて移動平均線に近づいたとき(シグナル2または3)**が絶好の買い場になります。
下降トレンドの基本パターン
- 高値・安値が切り下がっている(ダウ理論)
- 価格が移動平均線の下に位置(グランビル)
- MAは下向きに推移
この条件では、戻りが入ってMAに近づいたとき(シグナル6または7)が戻り売りのチャンスです。
トレンド転換の判断材料としても有効
- 波形が切り替わり、かつグランビルの1番 or 5番シグナルが発生
- MAの角度が横ばい→上向き(または下向き)に変化
このようなサインが重なれば、トレンド転換の初動に乗ることも可能です。
このように、「価格の波」と「移動平均線の位置関係・傾き」をセットで見ることで、一貫性のあるトレード判断ができるようになります。
グランビルの法則の限界と補足知識
どんなに優れた理論であっても、万能というわけではありません。
グランビルの法則にも限界があり、それを理解して使わなければ逆効果になることもあります。
このセクションでは、実際の運用で注意すべきポイントや、補完するための知識を解説します。
グランビルの法則は、トレンド相場では有効ですが、レンジ相場ではダマシが多発するのが最大の弱点です。
また、移動平均線自体が「遅行指標」であるため、すでに動いた後のサインしか出ないことも多いです。
このような弱点を補うには、次のような補足知識や工夫が必要です。
グランビル法則の“ダマシ”に注意
グランビルの法則で最も注意すべき落とし穴が、「ダマシ(false signal)」の存在です。
これは、シグナルが出たにも関わらず、相場が思った方向に進まずに逆行してしまう現象を指します。
特にレンジ相場や出来高が少ない時間帯では、このダマシが頻繁に発生します。
よくあるダマシの例
- シグナル1(上抜け)発生 → すぐにMAを割り込む
- シグナル5(下抜け)発生 → すぐに反発して上昇
こうしたパターンは、移動平均線の傾きが明確でないときに特に起きやすいです。
MAが横ばいの状態でシグナルが出た場合は、信頼性が低いため見送る判断も大切です。
ダマシを回避するポイント
- MAの角度を重視(しっかり上向き/下向きのときだけ使う)
- ローソク足の形状や出来高も確認
- 他のインジケーターで裏付けを取る
- トレンドの有無をまず確認(ダウ理論との併用が有効)
ダマシは完全に避けることはできませんが、「ダマシを前提にしたトレード設計」──たとえば損切り幅の調整や資金管理の徹底を行うことで、大きな損失を防ぐことができます。
うまく使うためのコツと習慣
グランビルの法則を単なる“知識”で終わらせず、実戦で使える“武器”に変えるためのコツと習慣をここでまとめておきます。
継続的に使っていく中で、自分なりの活用法に昇華していきましょう。
チャートを毎日観察する
グランビルのシグナルは、リアルタイムでチャートを見ていないと気づきにくいものもあります。
毎日チャートを眺めることで、自然とパターンが見えてくるようになります。
トレード日誌をつける
「どのシグナルで入ったか」「その結果どうだったか」を記録していくことで、自分に合うシグナル/合わない場面が見えてきます。
グランビルを自分仕様に最適化するには、日誌が最強のツールです。
組み合わせるインジケーターは1~2個に絞る
多くのインジケーターを並べすぎると混乱します。
RSI・MACD・ボリンジャーバンドなど、信頼できるものを厳選して併用するのが鉄則です。
“見送り”の判断もルールに入れる
「今はトレードしない方がいいな」という判断も立派な戦略です。
グランビルの法則はあくまで“チャンスを見つける手段”なので、シグナルが出ても環境が悪ければスルーする習慣をつけましょう。
最終的には、「シグナルを使うか使わないかを判断できる力」が勝敗を分けます。
そのために、日々の検証と改善を怠らないことが、FXで勝ち続ける鍵になります。
まとめ
グランビルの法則は、移動平均線と価格の位置関係をもとに8つの売買シグナルを判断するテクニカル手法であり、特にFX初心者が「どこで買えばいいのか」「どこで利益確定・損切りすればいいのか」といったタイミングの悩みを解決するために非常に役立つ考え方です。
本記事では、基本概念から8つのシグナルの具体的内容、それらを使う際の注意点や他のテクニカル指標との併用法、さらにはダウ理論との組み合わせまで、グランビル法則を使いこなすための一連の知識を体系的に解説しました。
重要なのは、「ただ覚える」のではなく、検証を重ねて自分のトレードスタイルに落とし込むことです。
相場環境は常に変化しますが、ルールを守りながら実践すれば、グランビルの法則はあなたのFX取引における強力な武器になるはずです。
ぜひ、自分のチャートで今日から試してみてください。